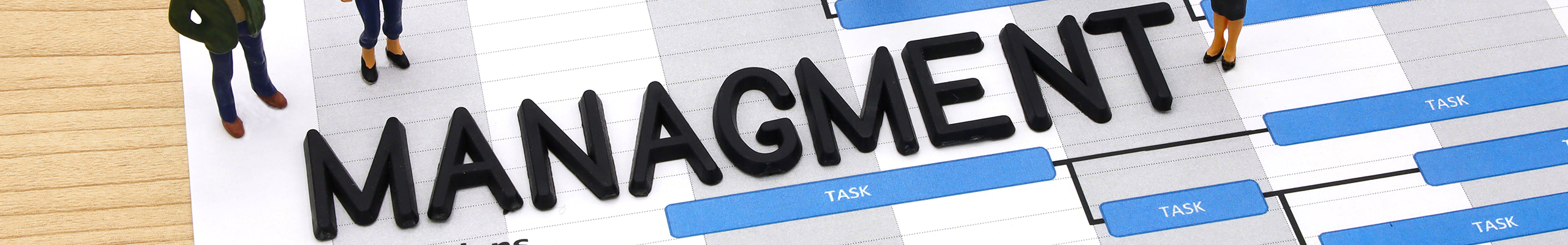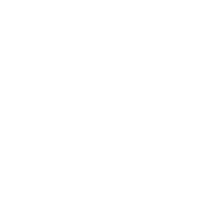〔第9講 **解説** 〕新規企画が出ない
<解説>
1.問題の本質
この事例の問題の本質は、田島課長が本来のマネジメントを実践できていない、ということである。
マネジメントを実践していくためには、管理者とは何か、マネジメントとは何をすべきかを理解しなければならない。
マネジメントとは組織の目標を達成するために、経営資源を効率的に活用することである。
そのために管理者の任務は何かの理解が重要である。
管理者の任務は基本的に2つある。
一つが目標・方針を設定し、これを職場に浸透させることである。
もう一つが、設定された目標に向けて構成メンバーの努力の方向を示し、動機づけすることである。
この事例では、製品企画部開発課としての目標方針が鮮明になっていない。
職場としてどのような方向に努力すべきかを明確化し、理解させなければチームとしてのパワーは発揮されない。
また、出された企画案についての管理者としての対応も問題である。
目標方針に向けての動機づけができていないのである。
逆に、やる気を失うような対応をしている。
さらには開発環境の整備も不十分である。
本来、部下が仕事の効率を上げるための環境整備は管理者の任務であり役割である。
それを部下がやるべきと逃げているようだ。
これでは部下のやる気を引き出すことはできない。
2.対応策
<開発課のビジョンを示す>
まずは、職場としてのビジョンを示すことが必要である。
職場のビジョンとは、「課長が考える職場としてのあるべき姿」である。
将来、職場をどのような姿にしたいのかをできる限り分かりやすい言葉で表現することが望ましい。
<開発課の目標・方針を明確化>
現状では目標方針が曖昧である。
職場としての目標方針を具体的に鮮明に設定し、この目標を達成するために各個人レベルでは何をするかを具体的に設定しなければならない。
職場の目標方針と個人レベルの目標が明確化することによりマネジメントを機能させることができるのである。
<開発環境の問題解決>
現状では企画案を出せる余裕がないということである。
すでに開発が完了し、量産に入っている製品のトラブルや、お客からのクレーム対応に追われている。
この状況を解決しなければならない。
この問題解決はスピードが要求される。
根本的な解決の方向としては、開発が完了し、量産に移行したものの問題が発生しないよう、現状の問題や原因を明確化し対策を実践することである。
その問題を解決すべき課題としては、組織的なテーマがありそうである。
開発を担当したメンバーが後々まで全てを面倒見る体制にムリがあるようだ。
この点における組織構造の見直しが必要となろう。
<動機づけ>
部下への動機づけの方法が必要である。
動機づけを実現するには部下とのコミュニケーションの機会を積極的につくり、十分なる話し込みが求められる。
もっと部下の考えを受け入れ、その考えを活かしていく方向が必要であろう。