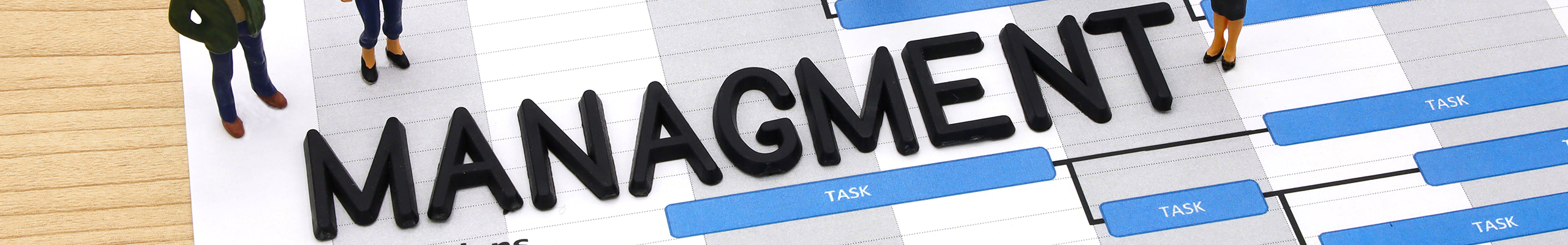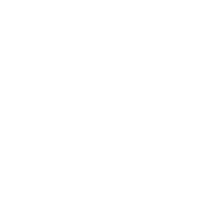〔第13講 **解説** 〕工場革新プログラムの失敗
<解説>
1.問題の本質
この事例における問題の本質は、工場の体質改善をどのように進めるべきかという点にある。
この事例のように、なにをやっても中途半端に終わってしまい、具体的な成果に結び付けていないケースでの体質改善は大変難しい。
どうせ何をやっても変わらないという意識が組織全体に蔓延しているからである。
このような意識のある組織において最初から高度で、成果がすぐに実感できない体質改善活動は適切ではない。
BPRなどの革新活動は、成果が目で見て分かりづらく、成果までに時間がかかるものである。
このような活動は、事例に書かれてある組織では適切ではない。
革新活動や改善活動の実行により、体質が変革できているという事実を素早く実感できる体質改善活動が有効である。
川崎工場長が、最後に気づいた工場革新の方向とは、基本動作の徹底ということであろう。
ゴミ箱の周囲に汚れが飛散している状況をみて、まずは、基本的なルールを確実に徹底できる組織風土がなければならないと気づいたのである。
どのような革新や改善活動をを展開しても決めたことを確実に実行する組織風土や文化がなければ、物事は前に進まないのである。
このような基盤づくりが、体質改善のスタートなのだと感じたのである。
2.対応策
この工場の事例において、組織の基本ルールを徹底できる基盤づくりの実現のために、まず、実行すべき項目は5Sの徹底であろう。
5Sとは職場環境の整理・整頓・清掃・清潔・しつけを全員参加で実践することである。
5Sということを理解していない人は、その効果を低く見積もってしまうことも多いが、組織体質改善のスタートとして取り組むには大変効果的である。
誰にでも分かり易いテーマであること、実践すれば短期間に職場環境の変化を実感できるものである。
また、具体的な成果としてさまざまなムダが削減できる。
身近なところで職場の変化や具体的な効果を実感することで、組織の体質改善のきっかけづくりとなる。
決めたことを決めた通りに確実に実行することの習慣づけを組織に植え付けることが重要である。
このような習慣づけが定着できて始めて、さまざまな革新活動も実行成果が上がってくる。
また、革新活動には、管理監督職クラスの強いリーダーシップと率先垂範が求められる。
5Sを徹底する活動を通じて管理監督者が部下を管理するための管理能力を高めることが期待できる。
このようなベーシックマネジメント力の強化がすべての基本である。